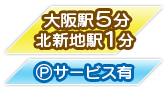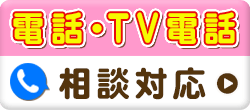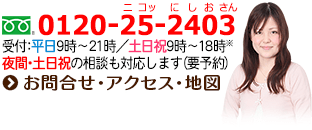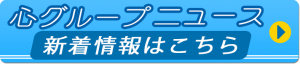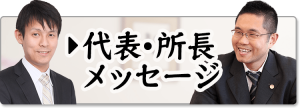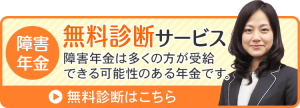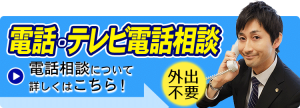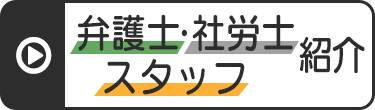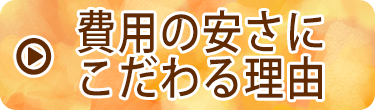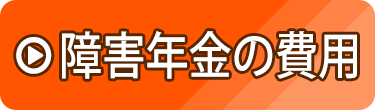くも膜下出血で障害年金を請求する場合のポイント
1 くも膜下出血によって生じる可能性のある障害について
くも膜下出血で障害年金を請求する場合の最初のポイントは、くも膜下出血と因果関係のある障害を漏れなく把握することです。
くも膜下出血は、言うまでもなく脳に影響を与える傷病であるため、多様な障害が残ります。
典型的には、半身麻痺のような肢体障害が残ることが考えられます。
しかし、肢体の障害に限らず、例えば、くも膜下出血を契機に、一気に認知機能が低下する高次脳機能障害といった障害もあります。
高次脳機能障害は、非常に症状を見落としやすい障害であり、記憶力や遂行機能など、高次の脳機能の一部だけが減退するケースもあります。
このように、一口にくも膜下出血による障害年金といっても、まずは、そのくも膜下出血によってどのような障害が残っているのかを漏れなく把握することが重要になります。
2 くも膜下出血で肢体障害が残った場合
くも膜下出血により肢体障害が残った場合には、個々の日常生活動作にどのような不自由があるのかを正確に医師に伝えて、それを障害年金の診断書に記載してもらうことがポイントとなります。
例えば、食事をする際の手の動きはできるかや、歩行に支障はないかなど、そういった一つ一つの動作について実態を把握することが肝心です。
3 高次脳機能障害が残った場合
高次脳機能障害は精神の障害に分類されています。
高次脳機能障害の場合、まず、認知面での異常に気付いたら速やかに医師に相談し、認知機能等のテストを受けることが重要です。
高次脳機能障害あらわれ方にも様々なものがあり、例えば、記憶障害が強く出て、新しい出来事を記憶する能力が大幅に減退してしまったりするなどの症状があらわれることがあります。
その他にも注意障害といって、注意力を維持することができなくなり、日常生活や仕事の多くのことにミスを連発してトラブルを起こすようになることもあります。
この他にも、性格面が変容し、社会的に不適切な行動をとるようになってしまったり、遂行機能障害といって自分自身で計画を立てて物事を計画通り遂行することができなくなるなどの症状がみられることもあります。
これらの変化は、身近な家族等でないと気づきにくいものです。
くも膜下出血を起こした後に治療を通して関係を持つようになった医療関係者だけでは、例えば性格の変化などは気づくことが困難です。
そのため、高次脳機能障害が疑われる症状に気づいた際には、速やかに医師に相談して検査を受けることが重要なポイントになります。
お役立ち情報
(目次)
- 大阪での障害年金の申請の進め方
- 障害年金を受給するためのポイント
- 障害年金申請の必要書類
- 障害年金の決定から支給まで
- 不支給通知が届いた場合
- 障害年金の事後重症請求
- 障害年金における初診日
- 病院が閉院によって初診日のカルテが残っていなかったが、障害年金の受給ができたケース
- 障害年金における社会的治癒とは
- 障害年金の配偶者加算
- 国民年金で障害年金2級が認定された場合の金額
- 障害年金の金額
- 働きながら障害年金を受給できる場合
- A型事業所で働いたら障害年金は支給停止になってしまうのか
- 障害年金と生活保護の関係
- 障害年金の受給要件
- 障害年金の時効
- 障害年金の種類
- 障害年金がもらえない理由
- 障害年金における障害認定日とは
- 障害年金受給中に新たな障害が発生した場合の対応方法
- 障害年金を受給することによるデメリット
- 障害年金を受給することのリスクはあるのか
- 過去に遡って障害年金の支給停止を解除した事例
- 精神疾患について障害年金が認められる基準
- うつ病と障害年金3級
- 知的障害の場合の障害年金における初診日
- てんかんで障害年金が受け取れる場合
- 新型コロナ後遺症で障害年金を受給できる場合
- 高次脳機能障害で障害年金が受け取れる場合
- アスペルガー症候群で障害年金が受け取れる場合
- くも膜下出血で障害年金を請求する場合のポイント
- 聴力の障害で障害年金が受け取れる場合
- 気管支喘息で障害年金が受け取れる場合
- 心臓にペースメーカーを入れている場合の障害年金
- 人工肛門で障害年金が受け取れる場合
- 難病で障害年金が受け取れる場合
- 筋ジストロフィーで障害年金が受け取れる場合
- 義足で障害年金は受給できるのか
- メニエール病で障害年金を請求する場合のポイント
- 精神疾患の障害年金の更新時の注意点
- 障害年金の額改定請求について
- 有期認定と永久認定について
- 障害年金と障害者手帳の違い
- 特別障害者手当
- 障害者手帳について
- 障害年金の更新
- 障害者年金
- 社会保険労務士とは
- 障害年金についてどこに相談すればよいか
受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒530-0001大阪府大阪市北区
梅田1-1-3
大阪駅前第3ビル 30F
0120-25-2403